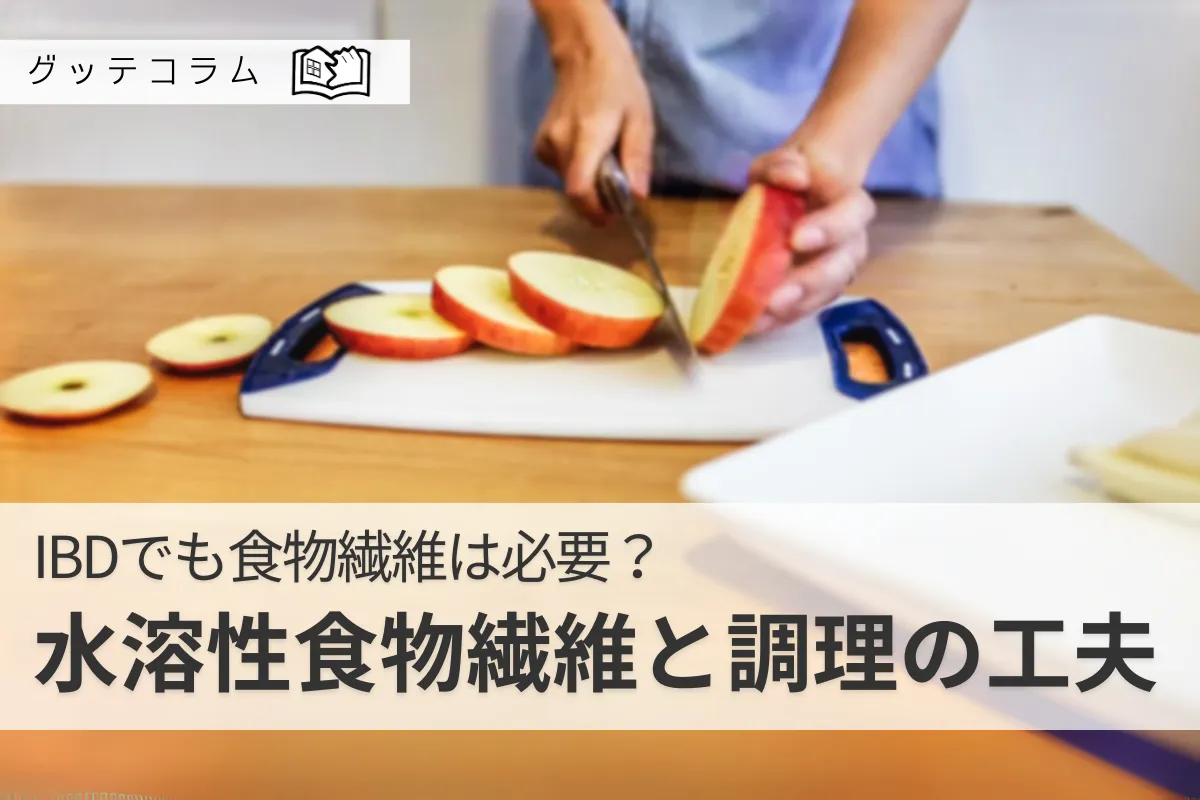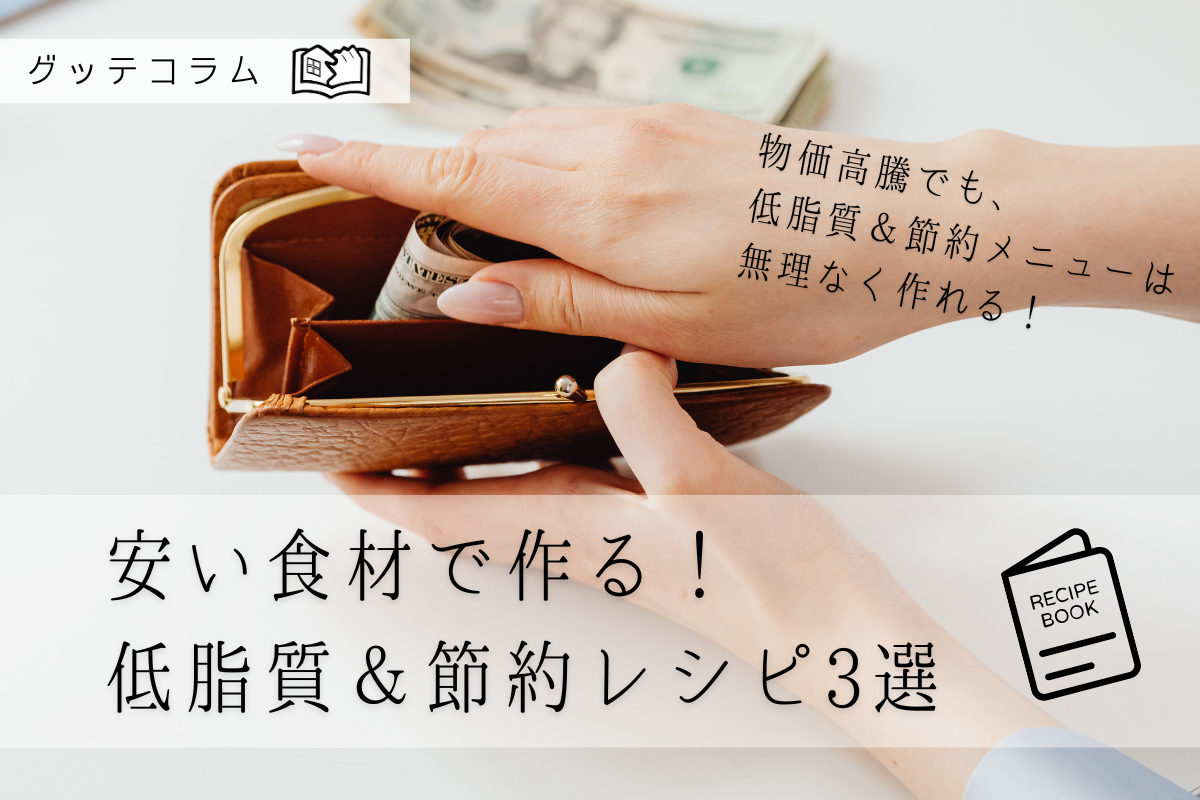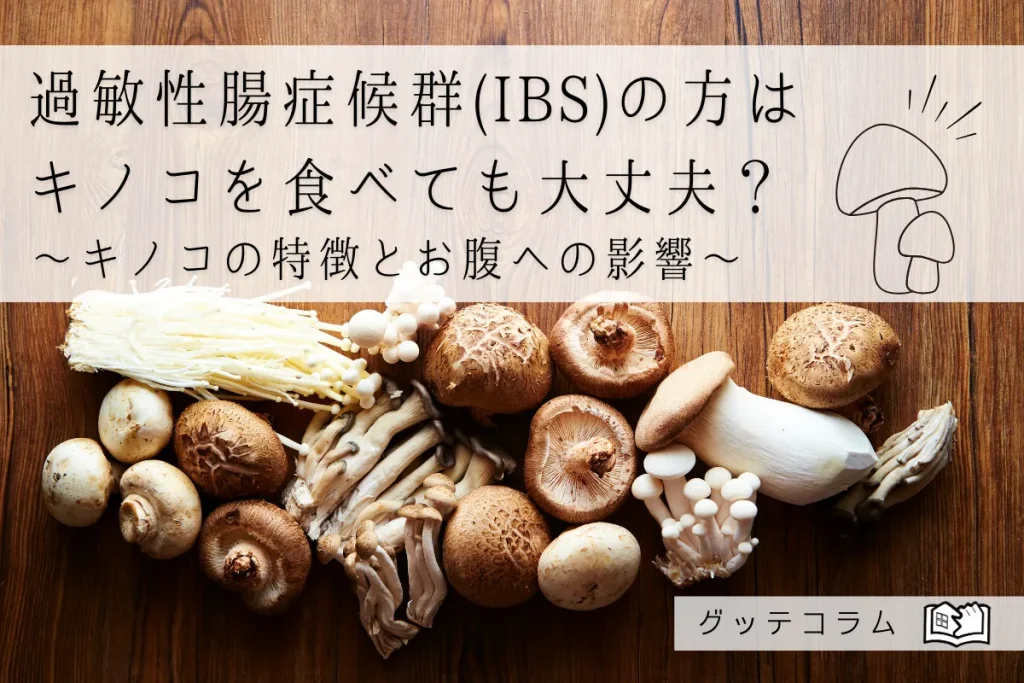
キノコ類は腸活によいと耳にすることが多く、意識して食べている方もいるのではないでしょうか?
では、過敏性腸症候群の方にとって最適な食品になるのかについて今回のコラムでお伝えしたいと思います。
キノコの栄養価
まずは、キノコの栄養価についてですが、しいたけ(100gあたり)の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に記載されている栄養成分は以下の通りです。
- エネルギー: 25kcal
- たんぱく質: 2.0g
- 脂肪: 0.2g
- 炭水化物: 0.7g
- 食物繊維総量: 4.9g
水溶性: 0.8g
不溶性: 4.2g - 糖アルコール(マンニトール): 1.2g
しいたけの主な特徴として、
たんぱく質や脂質、炭水化物などエネルギーの元となる栄養素が少ない(=低エネルギー)です。食物繊維が多く含まれ、主に不溶性食物繊維が多いことが分かります。
また、糖アルコールのマンニトールが1.2g/100g含まれています。
糖アルコールは人の消化酵素で消化されにくく、小腸で吸収されにくいのが特徴です。
食品だけでは一度にたくさん摂ることは難しいですが、甘味料として一度に多量に摂取すると、IBSなどお腹の症状が普段ない方でもお腹が一時的に緩くなることがあります。
しいたけ以外のキノコ類も栄養価に多少の違いはありますが特徴としては、大きく変わりはありません。

キノコが腸活によいといわれる理由
腸活とは、腸内環境をより良い状態にするために、食事に気をつけたり必要な運動をしたりする活動です。
「良い腸内環境」とは、腸内にいる細菌の量のバランスが保たれている状態で、これらのバランスを整えるのには腸内細菌のエサとなる食物繊維「プレバイオティクス」や、腸内細菌をいいバランスで増やすために乳酸菌などの「プロバイオティクス」を摂るといった方法があります。
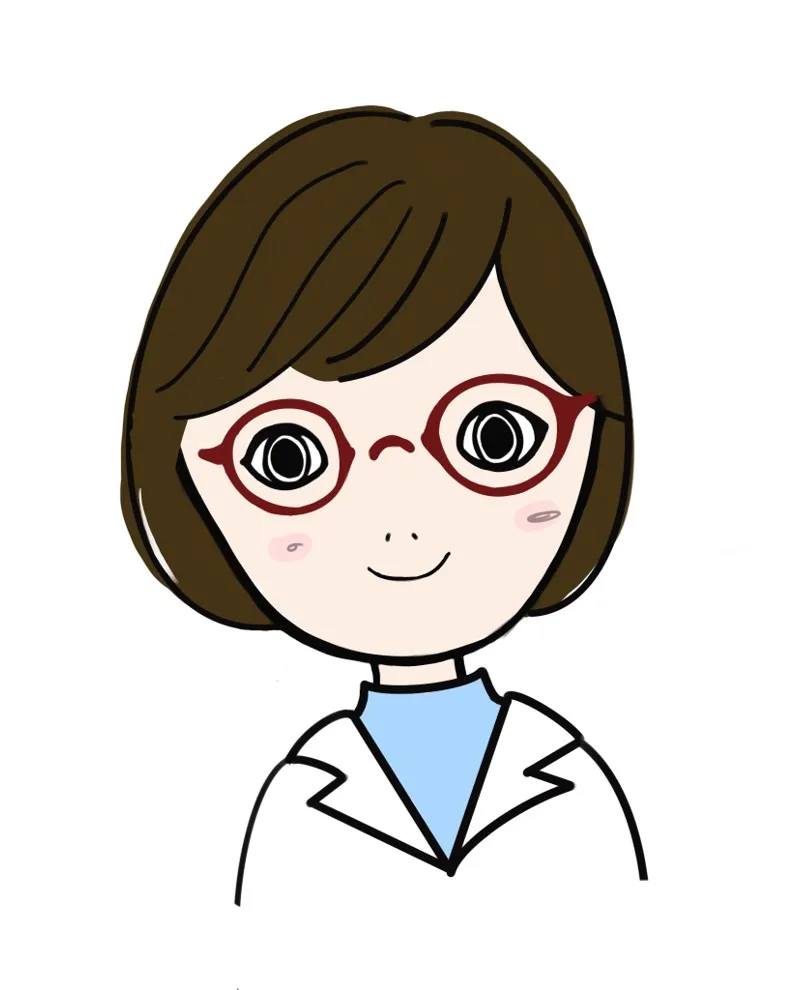
かおりさん
プロバイオティクス・プレバイオティクスについて詳しく知りたい方は過去のコラムも合わせてご覧ください。
キノコ類には、腸内細菌のエサの中で特に利用しやすい食品といわれている発酵性食物繊維が多く含まれていることから、腸活に有効と言えます。*1
過敏性腸症候群の改善に影響するか
キノコ類に多く含まれている不溶性食物繊維については過敏性腸症候群(IBS)の方の便秘の改善には有効ではあるが、それ以外のIBSの一般的な症状や腹痛に関しては悪化させたという報告があります。*2
また下痢の時にはキノコ類は、消化が良くないため避けた方が良いでしょう。
低FODMAP食との関係
キノコ類は発酵性食物繊維が多いことから、発酵性と聞くと食べるとお腹がゴロゴロするのではと気になる方はいるのではないでしょうか。
FODMAPのF「発酵性の」は発酵スピードが早い炭水化物のことを指していて、発酵性食物繊維のすべてがFODMAPが高いわけではなく、消化や発酵がゆっくり進む食品であれば問題はありません。*1
FODMAPのPは糖アルコールを差します。
ほとんどのキノコ類には糖アルコールの一種であるマンニトールが少量含まれていますが、食べてはいけないわけではなく、どのキノコも10g程度の量は低FODMAPの範囲です。
低FODAMP徹底期の方やマンニトールが合わない方は腸を調整する必要があります。低FODMAPのキノコ類をお探しの方はひらたけやきくらげを選ぶと量の制限がなく安心して食べることができます。
また、マッシュルームを水煮缶に加工するとFODMAPが減り低FODMAPの食材になることが分かっています。
キノコを使ったレシピの紹介
グッテレシピの中からキノコ類を使ったレシピをご紹介します。
豆腐ステーキ きのこあんかけ by あすかさん
万能塩きのこ by ねこ山さん
まとめ
今回のコラムでは過敏性腸症候群(IBS)の方向けにキノコ類がお腹にどう影響するかをまとめました。
どの食品も腸活によい、と同じ食品ばかりを食べるのではなく、お腹の症状に合わせて色々な食品を少量ずつ召し上がるのが腸内環境にとってはいいのではないかと思います。
グッテレシピからのお知らせ
グッテレシピでは引き続きご提供していただけるレシピを募集しています。いつもご家庭で作っているレシピ、イベント時のレシピなどぜひご提供ください。細かな量が分からない、作り方を書くことが難しい場合はグッテ管理栄養士でフォローする事も可能です。
下記のフォームもしくは、SNSのDMにてご連絡ください。ご提供お待ちしています。
⬇︎
監修者

宮﨑 拓郎
米国登録栄養士|公衆衛士学修士
Academy of Nutrition and Dietetics (米国栄養士会)所属 Registered Dietitian (登録栄養士)。ミシガン大学日本研究センター連携研究員。アメリカミシガン大学公衆衛生学修士(栄養科学)修了。大学病院等での勤務を経て米国登録栄養士取得。同大学病院消化器内科で臨床試験コーディネーターとして低FODMAP食の研究等に従事。帰国後コロンビア大学監修クリニックなどで保険適応外栄養プログラム立ち上げ、食事指導などに従事。講談社より「潰瘍性大腸炎・クローン病の今すぐ使える安心レシピ 科学的根拠にもとづく、症状に応じた食事と栄養」などを共著にて出版。ニュートリションケアなど管理栄養士向けの執筆多数。
執筆者
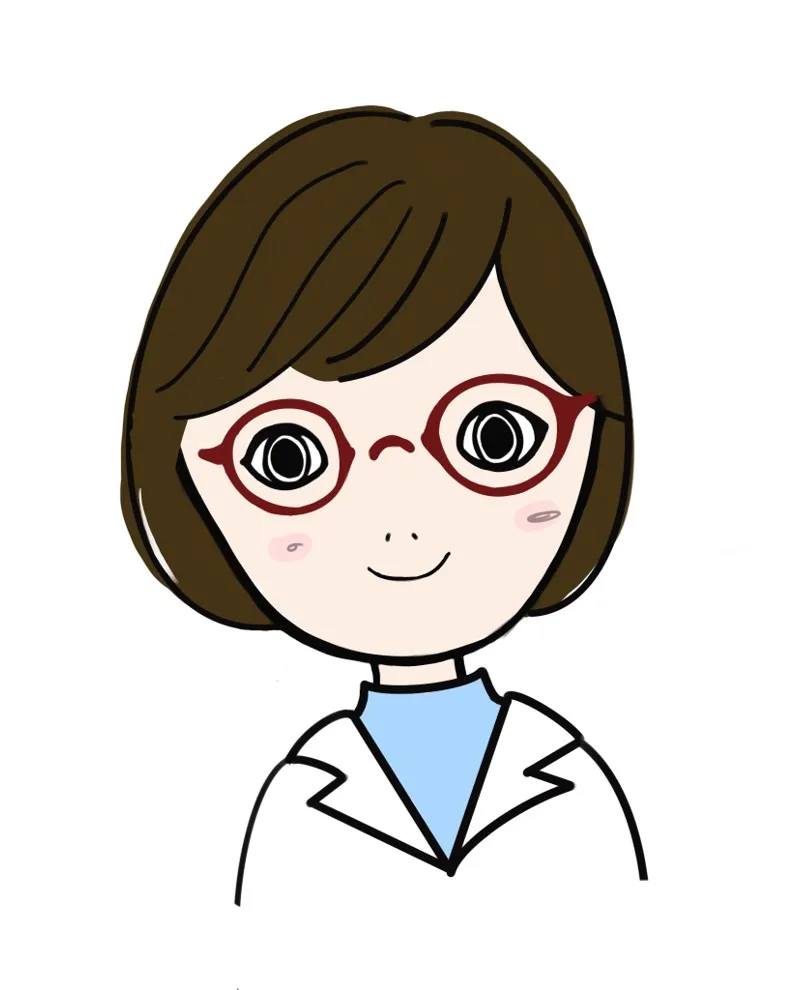
井本かおり
管理栄養士|日本栄養士会食
物アレルギー分野管理栄養士
管理栄養士として、病院、行政(学校給食)、こども園で主に献立作成、栄養指導、食育などに従事。家では過敏性腸症候群(IBS)の息子と一緒に低FODMAP食事療法を実践中。忙しい時にでも簡単においしく出来るレシピが得意です。
参考文献:
*1 内藤裕二(2024)『健康な土台をつくる腸内細菌の科学』日経BP
*2 過敏性腸症候群(IBS)診療ガイドライン2020