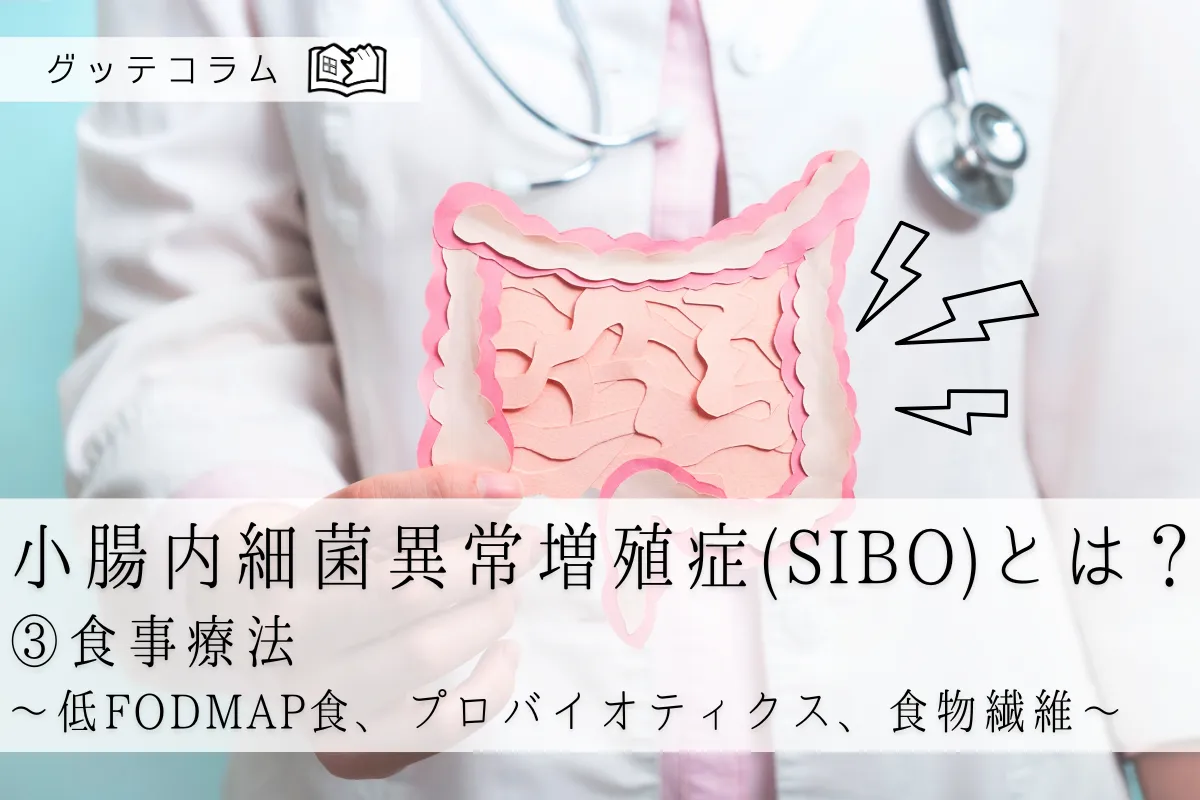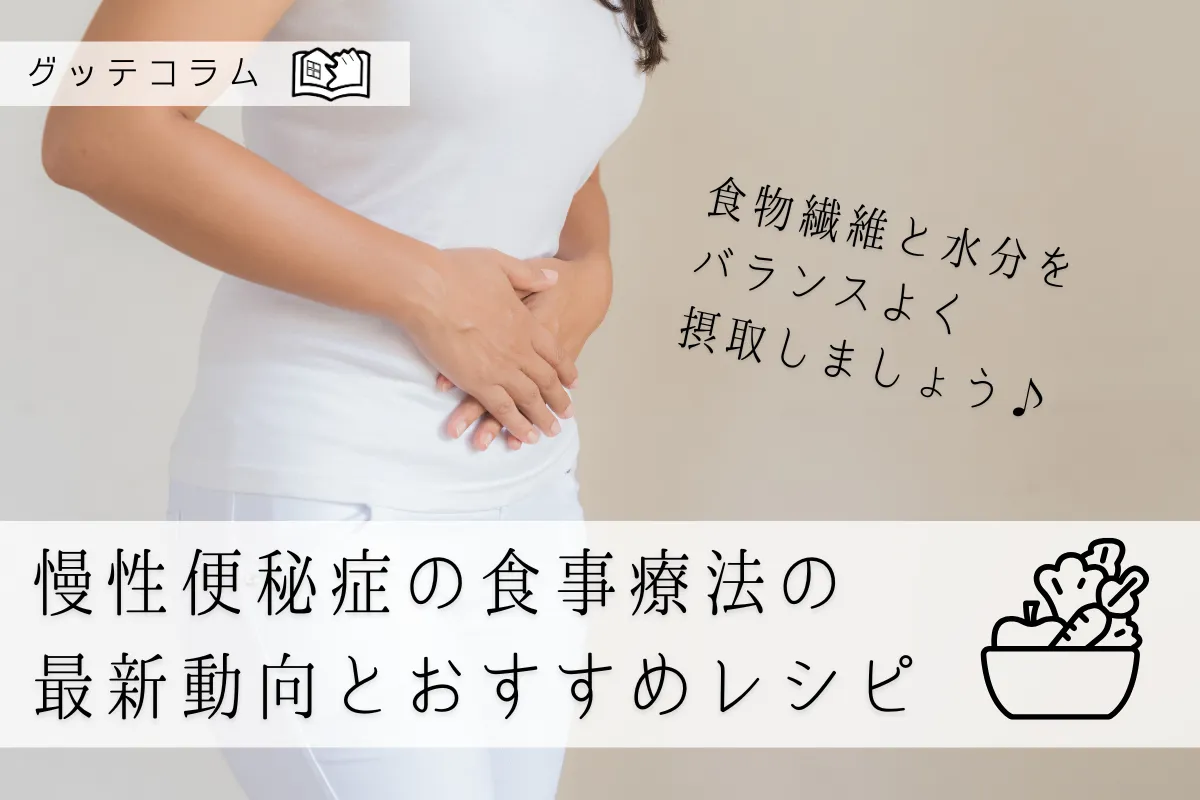執筆者:宮﨑 拓郎(米国登録栄養士)
- はじめに
- プロバイオティクスとは?
- プレバイオティクス 、シンバイオティクスとは?
- 過敏性腸症候群(IBS)に対する科学的エビデンスは?
- 潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)に対する科学的エビデンスは?
- おわりに
はじめに
今回はプロバイオティクスについて紹介します。プロバイオティクスという言葉はよく聞くけど、具体的にはイメージがわかないという方も多いのではと思います。今回は、プロバイオティクスの概要に加えて、過敏性腸症候群(IBS)や潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患(IBD)に対する研究についても紹介します。
プロバイオティクスとは?
プロバイオティクスとは、ヒトの腸内において、細菌のバランスを改善することによって健康に良い影響を与える微生物のことです。
いわゆる"善玉菌"と呼ばれる乳酸菌やビフィズス菌などが代表的なもので、みなさんも耳にすることが多いと思います。
食品ではヨーグルトや納豆、漬物などの中に含まれています。製品としてはヤクルトなどが有名ですよね。
クリニックや病院で処方されることの多いビオフェルミンやミヤBMなどもプロバイオティクスの一種です。
プレバイオティクス 、シンバイオティクスとは?
プレバイオティクスはプロバイオティクスのエサとなる食品成分です。
野菜や果物に含まれる食物繊維やオリゴ糖などがプレバイオティクスの代表例です。また最近はサプリメントなどでもプレバイオティクス が販売されていることがあります。
プロバイオティクスなどの善玉の腸内細菌がプレバイオティクスを食べることによって増殖し、より健康的な腸内細菌のバランスになります。逆にプレバイオティクス は体にとって有害な細菌を抑制する働きを持つことがあります。
さらにプロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせたものをシンバイオティクスと言います。
プロバイオティクスとプレバイオティクス が含まれたものの組み合わせもシンバイオティクスと呼べますし、様々なサプリメントも流通しています。
過敏性腸症候群(IBS)に対する科学的エビデンスは?
IBSに対する効果の検証としては食事よりもサプリメントについて盛んに研究が行われています。
中でもプロバイオティクスに関しての研究が最も多く行われており、プレバイオティクスの研究も一定数行われています。一方シンバイオティクスについてはまだあまり研究が行われていません。
プロバイオティクスのIBSに対する効果を検証した11本のランダム化比較試験の結果を元にしたシステマティックレビューでは、7つの試験で有意なIBS症状の改善が認められ、特に複数の菌種が含まれたプロバイオティクスや8週以上続けてプロバイオティクスを服用した場合において症状の改善が顕著に認められました。(1)
一方、アメリカ消化器病学会のプロバイオティクスに関するガイドラインでは、IBSに対する研究は多く行われているものの、試験設計など研究の質が低いことを理由にプロバイオティクスを推奨していません。(2)
なお、海外でIBSに対する効果が検証されている多くのプロバイオティクスのサプリメントは日本で販売されていないものとなります。
プロバイオティクスは菌種や量、貯蔵方法などさまざまなことに影響を受けると言われています。
日本で市販されている、処方されているプロバイオティクスがIBS患者に対して効果が検証されているわけではないので注意が必要です。
潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)に対する科学的エビデンスは?
IBDに対するプロバイオティクスの研究も盛んに行われています。
潰瘍性大腸炎
例えば、活動期の潰瘍性大腸炎では、菌株によってプロバイオティクスによる寛解導入効果が認められており、大腸菌 Nissle 1917株あるいはVSL#3*というプロバイオティクスが推奨されています。(3)
【注:いずれも現在日本では販売されていません】
*VSL#3:8種類の善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌、ストレプトコッカス属菌)の混合物
また、上記の2つのプロバイオティクスは寛解維持効果も認められており、潰瘍性大腸炎の寛解期においても海外で推奨されています。(3)
残念ながら、その他のプロバイオティクスについては、明確な臨床効果が認められていないため、ガイドラインでは推奨されていないのが現状です。
クローン病
クローン病においてもプロバイオティクスの研究は行われてきましたが、現在のところ明確な寛解導入効果および寛解維持効果は確認されておらず、プロバイオティクス投与は推奨されていません。(3)
なぜ潰瘍性大腸炎ではプロバイオティクスが有効で、クローン病では有効でないのか、その詳細な機序はわかっておりません。今後、新たなプロバイオティクスが開発される可能性もありますので、さらなる研究が期待されます。
おわりに
腸内環境を整えたい場合に、プロバイオティクスとプロバイオティクスのえさとなるプレバイオティクスの両方が必要となります。
では科学的エビデンスはどうかという点についてサプリメントに関する研究を見てみると、IBSに対する科学的エビデンスはまだ確立されておらず、IBDに関しては潰瘍性大腸炎で効果が確認されているものの、効果が確認されている菌株は日本で発売されていない状況です。
よって、科学的根拠の観点では無理してサプリメントを取る必要はありません。
もちろん、興味を持った製品があったら実際に試してみて、2-3ヶ月程度などと期間を切って、効果の有無を確認してみても良いと思います。ですが、一定期間摂取を続けても効果が実感できないプロバイオティクスを使い続ける必要はないでしょう。
またサプリメントを摂取しなくても、プロバイオティクスやプレバイオティクスは日頃よく目にする発酵食品や野菜や果物にも多く含まれています。
自分の体に合うプロバイオティクス・プレバイオティクスがあれば積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
監修者

今井 仁
東海大学健康管理学|消化器内科 講師
消化器専門医。医学博士。2009年に東海大学を卒業し横浜市立市民病院で初期臨床研修と消化器内科医として勤務開始。東海大学にて博士を取得後2017年米国ミシガン大学に留学し腸内細菌の研究に従事。帰国後も継続して腸内細菌の研究、消化器内科の仕事、健診センターの仕事を掛け持ちし日々研鑽を積んでいる。
執筆者

宮﨑 拓郎
米国登録栄養士|公衆衛士学修士
Academy of Nutrition and Dietetics (米国栄養士会)所属 Registered Dietitian (登録栄養士)。ミシガン大学日本研究センター連携研究員。アメリカミシガン大学公衆衛生学修士(栄養科学)修了。大学病院等での勤務を経て米国登録栄養士取得。同大学病院消化器内科で臨床試験コーディネーターとして低FODMAP食の研究等に従事。帰国後コロンビア大学監修クリニックなどで保険適応外栄養プログラム立ち上げ、食事指導などに従事。講談社より「潰瘍性大腸炎・クローン病の今すぐ使える安心レシピ 科学的根拠にもとづく、症状に応じた食事と栄養」などを共著にて出版。ニュートリションケアなど管理栄養士向けの執筆多数。
参考文献
- HF Dale, et al. Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: An Up-to-Date Systematic Review. Nutrients. 2019 Sep; 11(9): 2048.
- LS Grace, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Role of Probiotics in the Management of Gastrointestinal Disorders. Gastroenterology. 2020 Aug;159(2):697-705.
- Forbes A, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2017 Apr;36(2):321-347.